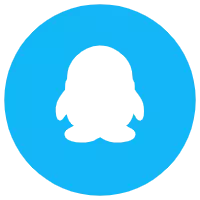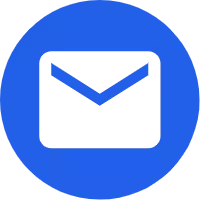- English
- Español
- Português
- русский
- Français
- 日本語
- Deutsch
- tiếng Việt
- Italiano
- Nederlands
- ภาษาไทย
- Polski
- 한국어
- Svenska
- magyar
- Malay
- বাংলা ভাষার
- Dansk
- Suomi
- हिन्दी
- Pilipino
- Türkçe
- Gaeilge
- العربية
- Indonesia
- Norsk
- تمل
- český
- ελληνικά
- український
- Javanese
- فارسی
- தமிழ்
- తెలుగు
- नेपाली
- Burmese
- български
- ລາວ
- Latine
- Қазақша
- Euskal
- Azərbaycan
- Slovenský jazyk
- Македонски
- Lietuvos
- Eesti Keel
- Română
- Slovenski
- मराठी
- Srpski језик
世界の炭素排出の現状: 炭素排出削減は緊急である
2025-07-09
国際エネルギー機関 (IEA) の 2025 年グローバル エネルギー レビューによると、エネルギー関連の CO₂ 排出量は 2024 年に 37.8Gt に達し、年間 0.8% の増加で過去最高を記録しました。同時に、地球の大気中の二酸化炭素濃度は 2024 年に約 422.5ppm に達し、2023 年から 3ppm 増加し、工業化前より 50% 増加しました。
土地利用を含む世界の総 CO₂ 排出量は 2024 年に 41.6Gt に達すると予想されており、これも過去最高となります。
この継続的な上昇傾向により、世界の気温はパリ協定で定められたレッドライン1.5℃に近づきつつあります。気候科学者らは、迅速な排出削減措置を講じなければ「臨界点」を引き起こし、壊滅的な結果を引き起こす可能性があると警告している。
排出削減への道:どこから始めるべきか?
1. エネルギーシステムの脱炭素化
IEAは、世界のエネルギー部門は依然として排出量を増加させているものの、再生可能エネルギー(太陽光と風力)が約2.6GtCO₂の排出削減潜在力に貢献していると指摘した。
ヨーロッパでは、電気自動車 (BEV) はガソリン車よりもライフサイクルの温室効果ガス排出量が 73% 低く、環境に優しい交通手段が促進されています。
2. 制約の厳しい産業における二酸化炭素回収 (CCS)
セメント生産は世界の CO₂ 排出量の約 8% を占めます。ノルウェーのベリビクにあるハイデルベルグ マテリアルズ セメント工場では、CCS 技術を使用して年間 400,000 トンの CO₂ を回収し、貯蔵しています。
3. 政策ツール: 炭素税と排出量取引
研究によると、炭素税を CO₂ 1 トンあたり 10 ドル増やすと、一人当たりの排出量を短期的には 1.3%、長期的には 4.6% 削減できることが示されています。
4. 自然な解決策と公正なメカニズム
ブラジルのピアウイ州は、森林破壊を削減することで毎年 2,000 万トンの炭素クレジットを生成し、官民パートナーシップを通じてそれを実行することを計画しています。
UNEPは、2030年までに森林などの自然手段を通じて約31Gt CO₂eを削減でき、2023年には世界の排出削減可能量の52%を占めると指摘した。
課題に直面しても方向性は明確
世界の総排出量は過去最高を記録しているが、IEAは先進国の排出量が減少し(欧州は2.2%減、米国は0.5%減)、デカップリングの傾向が現れていると指摘した。しかし、発展途上国(特にインドと東南アジア)での排出量は依然として増加しています。
ロイター通信は、2025年から5年ごとに排出量を半減した場合、世界が気温上昇を1.5℃抑制することしか期待できないと気候科学者が警告していると伝えた。これは、排出量を毎年平均12%削減する必要があることを意味する。
UNEPの「排出ギャップ報告書」はまた、目標を達成するためには世界経済に大規模な投資が必要であり、水力発電、効率化、自然システム保護を直ちに開始しなければならないと指摘した。
どのように実装すればよいでしょうか? 5つの主要戦略
1. 定量的な排出目標と段階的な排出削減経路を確立する
「最小コスト」または「フェアシェア」モデルを使用して、業界/国の 2030 年、2035 年、2050 年の目標を構築します。
2. 再生可能エネルギーと電動モビリティの拡大を加速する
エネルギーの脱炭素化と交通システムの電化を明確に優先します。 EU の電気自動車は、大幅な排出削減成果を達成しています。
3. カーボンプライシングと市場メカニズムを組み合わせる
炭素税とETSを主流に導入します。価格設定は長期的にはインセンティブを提供し、世界的な競争への短期的な影響を回避する必要があります。
4. CCS、BECCS等の技術の推進
セメントや鉄鋼など脱炭素化が難しい産業では、成熟した回収技術を推進し、国境を越えた保管・運用システムを構築する。
5. 自然資本の強化:森林、農業など。
ピアウイプロジェクトなど、明確な権利と責任を伴う森林保護炭素クレジットプロジェクトを支援します。同時に、農業の低炭素変革と自然生態系の回復を促進します。
行動は急務です
炭素排出量は依然として新記録を樹立していますが、既存の技術や政策ツールがないわけではありません。重要なのは次のとおりです。
明確で定量的な目標を設定します (5 年、10 年、30 年)。
電化、カーボンプライシング、CCS、自然保護の併用。
公平な分配メカニズムを形成するために国と地域の協力を強化する。
ロイター通信が強調したように、「気候変動が5年ごとに半減する場合にのみ、世界はこの気候変動競争に勝つことができる」。これが私たちが現在直面している課題であり、唯一実現可能な道でもあります。政策、テクノロジー、公正なメカニズムを相乗的に前進させ、「ネット・ゼロ」への道を共同で紡ぎましょう。